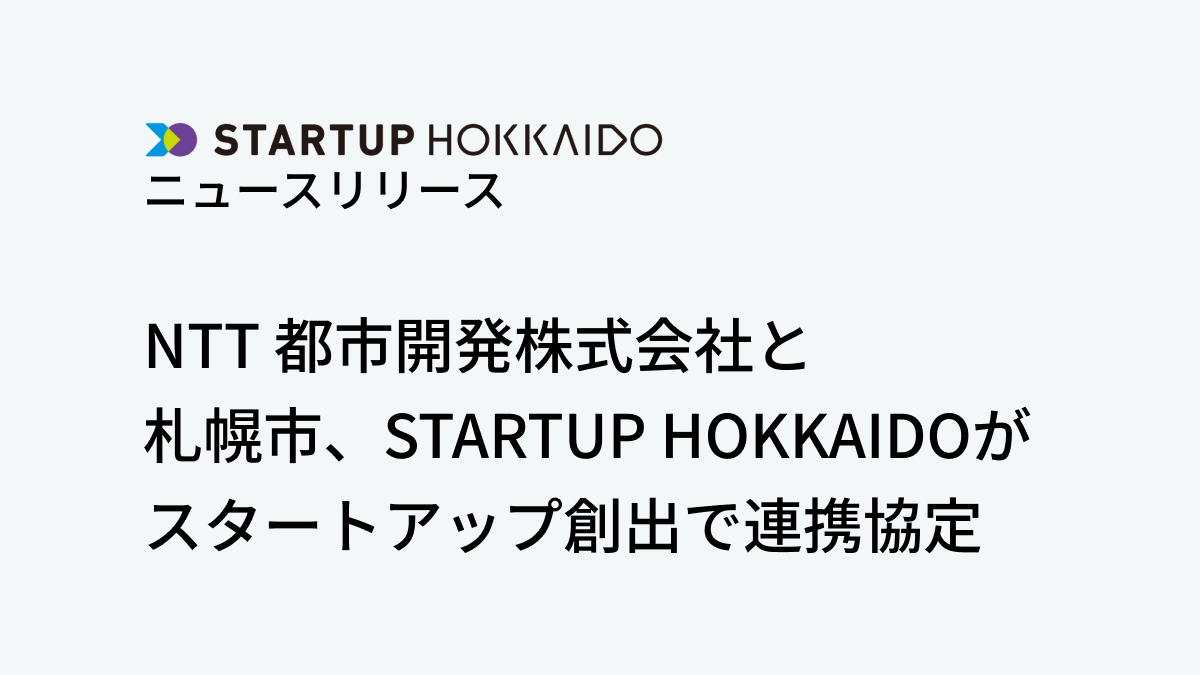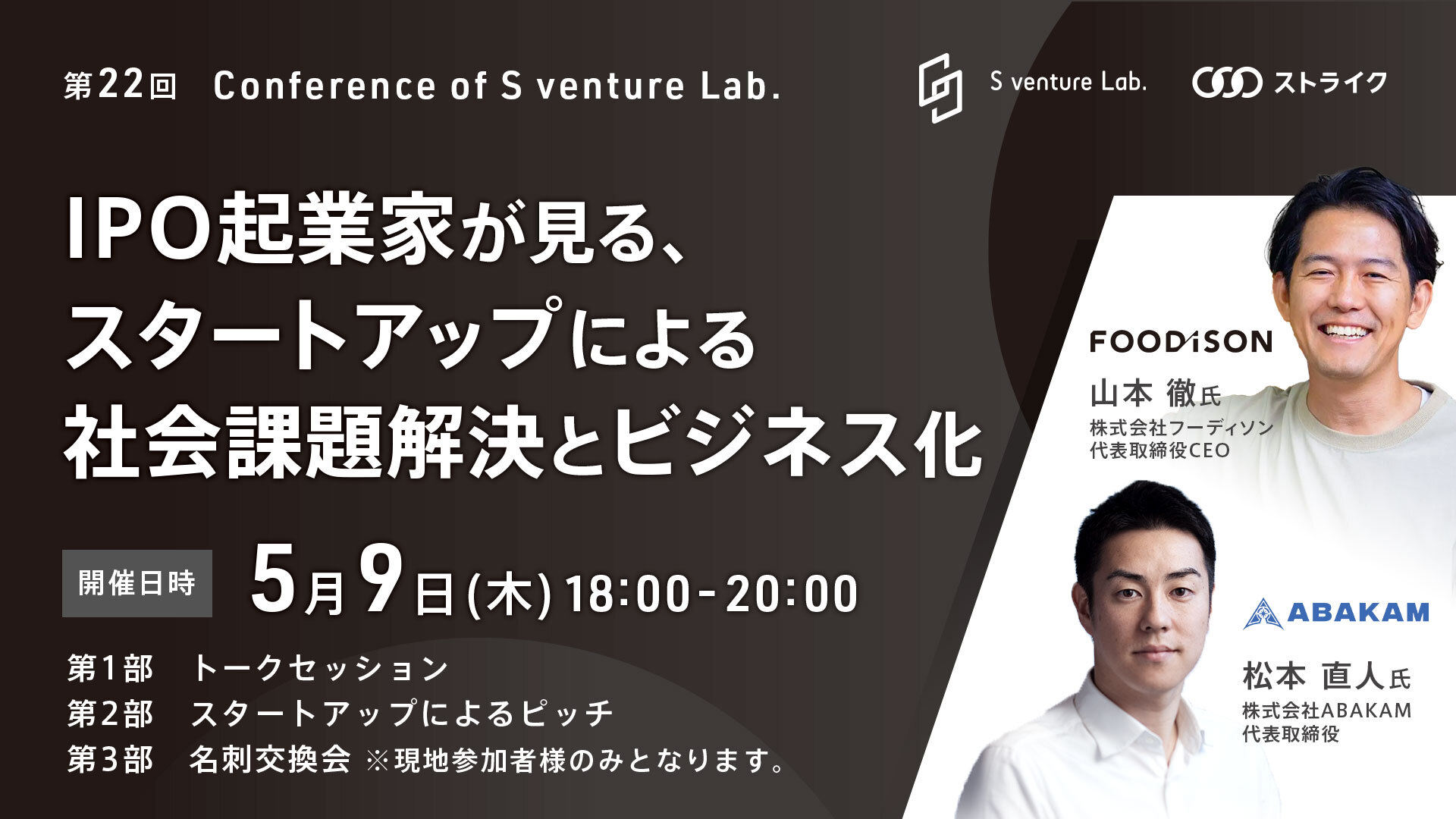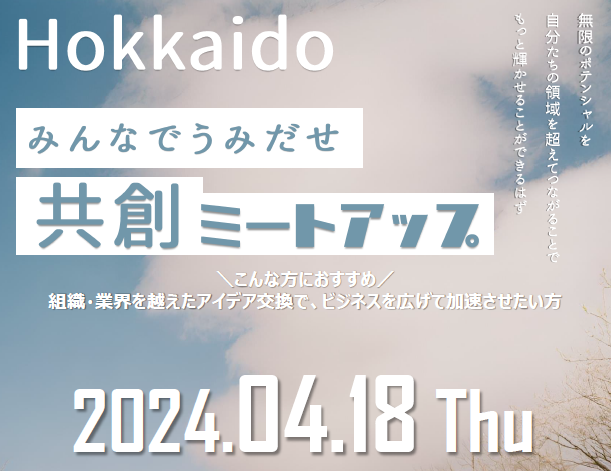起業を考えている方・すでに事業を進めている方の相談
STARTUP Consulting
事業相談や士業への相談ができる相談を受け付けています。
対面やオンラインどちらの相談も可能です。
ぜひお気軽にご相談ください!
どちらも対象です。
スタートアップ相談について
- これからスタートアップを創業する方
- すでにスタートアップを創業した方

ABOUT US
STARTUP HOKKAIDOについて
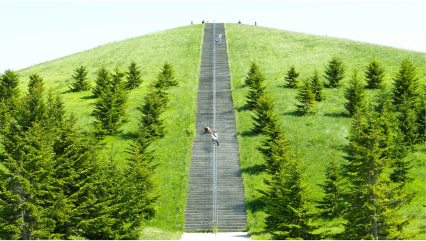
大志を抱け、この場所で。
私たちスタートアップ北海道は北の大地を、起業したい人が集まり、つながり、世界を驚かす事業が次々と生まれる場所へと変えていく。
詳しく見る