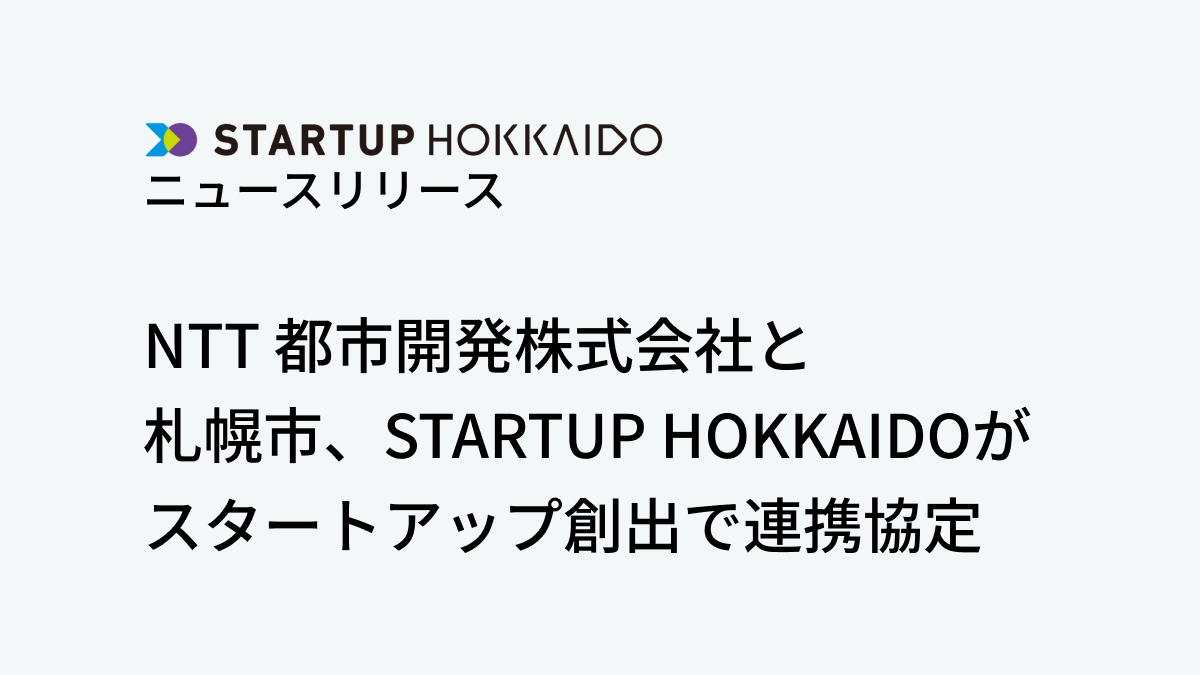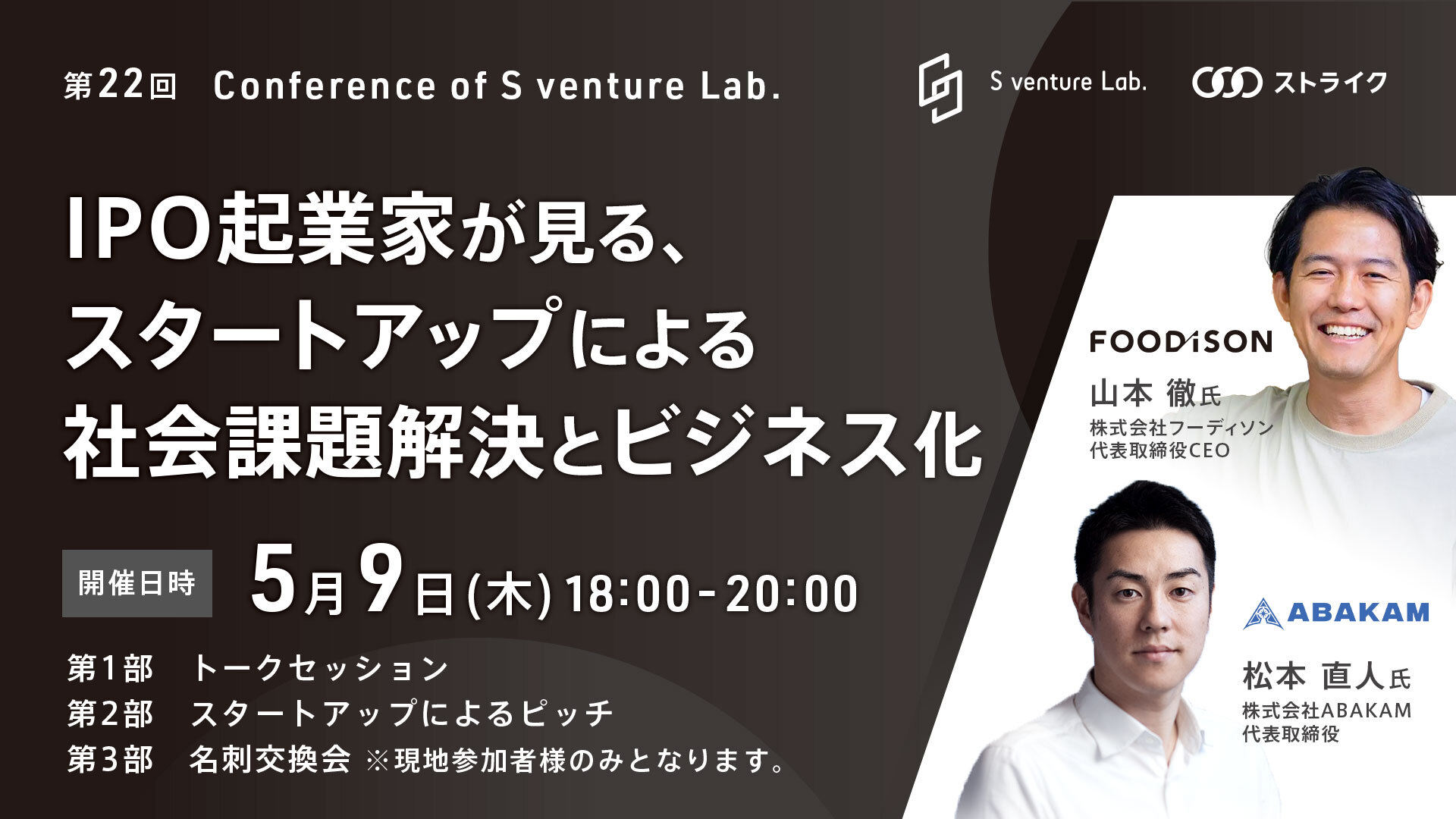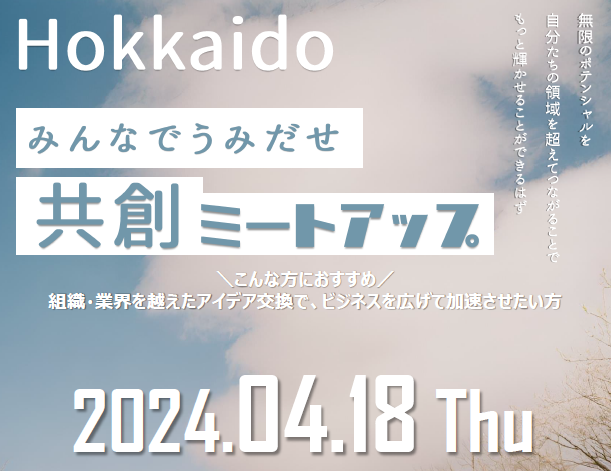-
2024SPACE COTAN、北海道オプショナルツアーズ、日本旅行が北海道スペースポートで民間宇宙開発を学ぶツアー販売開始 READ04/22 (Mon)
-
2024総額8.4億円の資金調達を実施 READ04/19 (Fri)
-
2024LIFE CREATE 新たな役員体制で事業成長をさらに加速~ウェルネスで、女性の未来を創る~全国100店舗以上、女性専用ブティックスタジオジムを運営 READ04/18 (Thu)
-
2024民間にひらかれた商業宇宙港「北海道スペースポート」プロジェクトに企業版ふるさと納税で新たに35社、2億8,865万円の寄附 READ04/17 (Wed)
起業を考えている方・すでに事業を進めている方の相談
STARTUP Consulting
事業相談や士業への相談ができる相談を受け付けています。
対面やオンラインどちらの相談も可能です。
ぜひお気軽にご相談ください!
どちらも対象です。
スタートアップ相談について
- これからスタートアップを創業する方
- すでにスタートアップを創業した方

ABOUT US
STARTUP HOKKAIDOについて
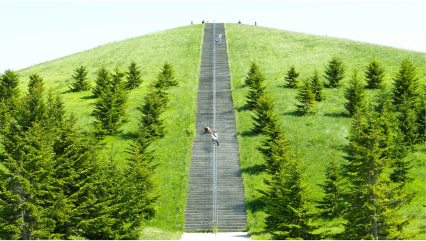
大志を抱け、この場所で。
私たちスタートアップ北海道は北の大地を、起業したい人が集まり、つながり、世界を驚かす事業が次々と生まれる場所へと変えていく。
詳しく見る